
近年、スマートフォンやSNSの普及により、誰もが気軽に写真や動画を撮影・共有できるようになりました。その一方で、「盗撮」や「リベンジポルノ」といったデジタル性犯罪も増加し、社会問題となっています。
このような背景から、2023年7月13日、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」、通称「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。これは、これまで各都道府県の迷惑防止条例に委ねられていた盗撮行為を、全国一律で厳しく取り締まるための法律です。
今回は、この法律のポイントを中小企業診断士・労務士の視点からわかりやすく解説し、企業や働く人々が知っておくべきリスクと対策について考えていきます。
LINEUP1:盗撮だけじゃない!4つの類型で厳罰化された「撮影罪」
これまでの盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例によって取り締まられていました。そのため、地域によって罰則や処罰の範囲が異なったり、航空機内など場所によっては取り締まることが難しかったりといった問題がありました。
しかし、この新しい法律「性的姿態撮影等処罰法」によって、全国一律の基準で盗撮行為が処罰されることになりました。特に注目すべきは、単なる「盗撮」だけでなく、以下の4つの類型に分けて処罰の対象が拡大されたことです。
- 盗撮:気づかれないよう性的部位や下着、性行為中の姿態を撮影。
- 不同意撮影:暴行・脅迫や意識喪失状態などで同意を得られないまま撮影。
- 誤信による撮影:医療行為や限定公開などと誤解させて撮影。
- 16歳未満者の撮影:年齢や年齢差に応じて性的姿態を撮影する行為。
01. 同意があってもNGになる!?「不同意撮影」と「誤信による撮影」
従来の盗撮のイメージは「ひそかに、相手に気づかれないように撮影する」ことでした。しかし、この法律では、たとえ相手がその場にいて同意しているように見えても、「不同意撮影」や「誤信による撮影」として処罰されるケースがあります。
例えば、以下のようなケースがこれに該当します。
- 不同意撮影: 酩酊状態の同僚を、合意なく撮影する。
- 誤信による撮影: 「記念撮影だ」と嘘をついて、性的な部位が写るように撮影する。
これらの行為は、相手が明確に「NO」と言っていなかったとしても、暴行や脅迫、アルコールや薬物による意識不明瞭な状態に乗じて行われた場合、撮影罪となります。
02. 16歳未満を狙う行為も処罰の対象に
法律では、16歳未満の子どもを対象とした撮影行為も厳しく処罰されます。特に、13歳未満の子どもを撮影する行為は、同意があっても処罰の対象となります。また、13歳以上16歳未満の子どもに対しては、撮影者が5歳以上年上である場合、同意の有無にかかわらず処罰されます。
これは、子どもが性的な被害に遭いやすい状況を考慮し、特に保護を強化する目的があります。
03. 撮影罪の罰則と再犯率の高さ
この法律における撮影罪の罰則は、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」と、以前の都道府県条例に比べて厳しくなっています。
さらに、驚くべきは盗撮の再犯率の高さです。令和6年の犯罪白書によると、刑法犯検挙人員に占める再犯者率は47.0%と比較しても、盗撮の再犯率は28.6%と、性犯罪類型の中では高い水準を示しています。
これは、盗撮行為が依存性のある行為である可能性を示唆しており、単なるいたずらでは済まされない深刻な問題であることを物語っています。
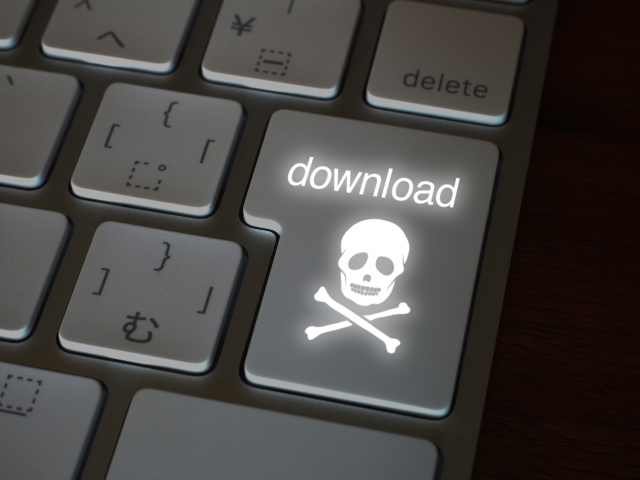
LINEUP2:撮影するだけじゃない!「提供罪」「記録罪」も処罰対象に
性的姿態撮影等処罰法は、撮影行為そのものだけでなく、撮影された画像や動画の取り扱いについても厳しく規制しています。
01. リベンジポルノからライブストリーミングまで
これまでもリベンジポルノ規制法はありましたが、この法律では、撮影された性的姿態の画像を他人に提供したり、インターネット上で公開したりする行為を「提供罪」として処罰します。提供の対象が特定少数であっても、不特定多数であっても罰則が科されます。
また、近年のライブ配信の増加を受けて、「影像送信罪」も創設されました。これは、盗撮した映像をリアルタイムで不特定多数の人に送信する行為で、罰則は「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」と非常に重いものになっています。
02. 「見て見ぬふり」も罪になる可能性
さらに、この法律で注目すべきなのが「記録罪」です。これは、ライブ配信されている盗撮映像を、その事情を知った上で録画する行為を罰するものです。
「自分は撮影していないから関係ない」と考えるのは危険です。盗撮映像を録画する行為も、この法律では犯罪となります。これは、デジタル性犯罪の被害を拡大させないための重要な規定です。
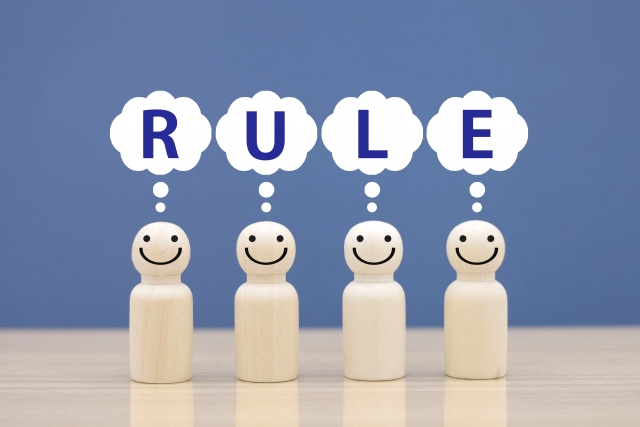
LINEUP3:企業が取るべき対策と従業員への周知
性的姿態撮影等処罰法は、個人の行動だけでなく、企業にも大きな影響を与えます。もし従業員がこの法律に違反した場合、それは単なる個人的な問題ではなく、企業の社会的信用を大きく損なう事態に発展する可能性があります。
01. 企業リスク
「プライベートだから関係ない」という時代は終わりました。当然社外での行為も企業リスクになり得、SNSや報道で会社名が出れば、取引停止や顧客離れは現実的なリスクに繋がります。特に営業・接客業など対外的接点の多い業種は影響が大きくなります。
企業が放置すれば、損害賠償や厚労省からの指導、報道による信用失墜が避けられません。また業務中の違法行為では法人も処罰され、さらに使用者責任により民事賠償請求を受ける可能性があります。
02. 就業規則の見直しと懲戒処分の明確化
従業員が職場内外で撮影罪を犯した場合、会社として適切な対応を取る必要があります。まず、就業規則に「性的姿態撮影等処罰法」に違反する行為を懲戒処分の対象とする旨、明確に記載することが重要です。
盗撮行為は、被害者である従業員に深刻な精神的苦痛を与えるだけでなく、社内の秩序を乱し、職場環境を悪化させる行為です。企業は、こうした行為を許さないという毅然とした態度を示す必要があります。
03. 従業員への研修と周知徹底
この法律は施行されたばかりで、内容を十分に理解していない人も少なくありません。そのため、企業は定期的にハラスメント研修やコンプライアンス研修を実施し、従業員にこの法律の内容を周知徹底させるべきです。
特に、以下のようなポイントを伝えることが大切です。
- 盗撮だけでなく、不同意の撮影も処罰の対象となること。
- 被害者が子どもである場合、同意があっても犯罪になること。
- 撮影した映像をSNSなどで安易に共有・公開することが重い罰則につながること。
- 盗撮映像を録画する行為も犯罪となること。
これらの周知を通じて、従業員一人ひとりがデジタル性犯罪のリスクを理解し、適切な行動をとれるように促すことが、企業の信頼を守る上で不可欠です。
LINEUP4:まとめ
「性的姿態撮影等処罰法」は、デジタル社会における性犯罪の多様化に対応し、被害者を保護するために作られた重要な法律です。これまでの「盗撮」という概念を大きく超え、撮影行為そのものだけでなく、その後の画像の取り扱い、さらには子どもへの加害行為に至るまで、広範囲にわたって厳しく処罰の対象を定めています。
従業員が加害者とならないよう、そして被害者を出さないよう、企業は就業規則の整備や研修の実施を通じて、明確なメッセージを発信していくことが求められます。
デジタルツールがますます身近になる現代において、この法律の内容を正しく理解し、従業員一人ひとりの意識改革を促すことが、健全で安全な職場環境を築くための第一歩となるでしょう。
ジェイエスティーでは、企業のコンプライアンス体制構築やハラスメント研修など、危機管理に関する各種サービスを提供しております。専門家による実践的なアドバイスで、貴社のリスク管理体制強化をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
今回のコラムは、以下の顧問の方にご監修いただきました。
西岡 敏成
ジェイエスティー顧問
・元兵庫県警警視長
・警備・公安・刑事に従事
・2002年日韓W杯警備を指揮後、姫路警察署長・播磨方面本部長を歴任
・元関西国際大学人間科学部教授
ジェイエスティーには危機管理エキスパートが複数在籍しております。
コンプライアンス体制の構築や研修はもちろん、個人情報保護や暴対法対策など、危機管理全般のご相談はジェイエスティーまで。
