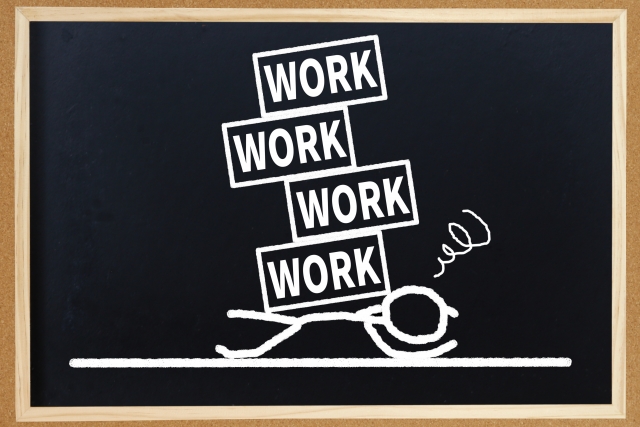
はじめに
「気がつけば深夜、休日出勤も当たり前。もう何のために働いているのか分からない…」
近年、このような悲痛な叫びをニュースやSNSで目にする機会が増えています。特に中小企業においては、慢性的な人手不足を背景に、従業員一人ひとりにかかる業務負荷は増大し、長時間労働が常態化している現場も少なくありません。その結果、心身の限界を超えて精神障害を発症したり、最悪の場合、過労死という痛ましい事態に至るケースが後を絶たないのです。
厚生労働省の調査では、週60時間以上働く労働者の割合は依然として高く、精神障害による労災認定件数は増加傾向にあります。これは決して他人事ではありません。あなたの会社の従業員も、疲弊しきった心で、誰にも言えないSOSを発しているかもしれません。「うちの会社は大丈夫」という楽観は、今すぐ捨て去るべきです。
本コラムでは、過労死という悲劇を防ぎ、かけがえのない従業員の命と健康を守るために、企業が今すぐに取り組むべき対策を具体的に解説します。
1.過労死の定義と深刻な現状
(1)「過労死等」とは何か
過労死は、単に「働きすぎて亡くなること」ではありません。法律(※)では、「業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡」や、「業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡」などと定義されています。死亡に至らない場合でも、これらの疾患や精神障害を発症することは「過労死等」に含まれます。
(※)2014年(平成26年)11月1日に施行された「過労死等防止対策推進法」
厚生労働省の発表によると、精神障害による労災支給決定件数は高水準で推移しており、2023年度には過去最多を更新しました。その中には、自ら命を絶つという最も痛ましい結果も含まれています。これらは氷山の一角に過ぎず、水面下で苦しんでいる人はさらに多いと推測されます。
(2)過労死を引き起こす3つの要因
過労死の背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。主な要因は以下の3つです。
ア 限界を超える「長時間労働」
過労死ライン(発症前1ヶ月間に100時間超、または2~6ヶ月間平均で月80時間超の時間外労働)に達するような長時間労働は、脳・心臓疾患のリスクを著しく高めます。令和5年の調査でも、週60時間以上働く雇用者の割合が約8%にのぼり、依然として多くの人が過重労働に苦しんでいる実態があります。
イ 心を蝕む「メンタルヘルス不調」
過剰な業務量、複雑な人間関係、将来への不安といった強いストレスは、うつ病などの精神障害を引き起こす大きな要因です。令和5年の調査では、実に労働者の8割以上が仕事で強いストレスを感じていると回答しています。精神的な疲弊は、判断力や集中力を奪い、最悪の場合、自死という悲劇に繋がります。
ウ 見過ごせない「ハラスメント」の存在
パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどの行為は、被害者の尊厳を深く傷つけ、心に大きなダメージを与えます。ハラスメントが放置された職場は、従業員のエンゲージメントを低下させ、離職率を上昇させるだけでなく、精神的な苦痛からメンタルヘルス不調を悪化させ、過労死の間接的な引き金となる可能性も否定できません。
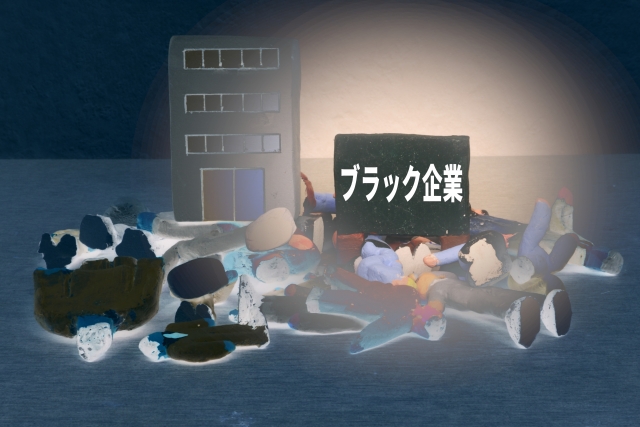
2.過労死が企業にもたらす、取り返しのつかない影響
企業内で過労死が発生した場合、そのダメージは計り知れず、企業の存続そのものを揺るがしかねません。
(1)かけがえのない人材の喪失と遺族への加害
言うまでもなく、従業員の命が失われることは最大の損失です。そして、企業は深い悲しみの中にいるご遺族に対して、重大な責任を負うことになります。
(2)社会的信用の失墜とブランドイメージの毀損
「ブラック企業」という烙印を押され、社会的信用は地に堕ちます。顧客や取引先が離れ、採用活動は困難を極め、既存社員の離職も加速するでしょう。
(3)職場環境の悪化と生産性の低下
従業員が亡くなったという事実は、他の従業員に深刻な動揺と不安を与えます。職場の士気は低下し、組織全体の生産性も著しく悪化します。
(4)行政からの指導・処分
労働基準監督署から厳しい調査を受け、改善指導や是正勧告が出されます。場合によっては、企業名が公表されることもあります。
(5)民事上の巨額な損害賠償責任
ご遺族から安全配慮義務違反を問われ、損害賠償請求訴訟を起こされる可能性があります。数千万円から1億円を超える賠償金の支払いを命じられるケースも少なくありません。
(6)経営者個人が問われる刑事罰のリスク
悪質なケースでは、労働基準法違反や業務上過失致死傷罪などで経営者や管理職が送検され、刑事罰を科される可能性もゼロではありません。

3.今すぐ始める「過労死ゼロ」への具体的な対策
過労死を未然に防ぐため、企業は具体的に何をすべきなのでしょうか。ここでは、3つの側面から対策を解説します。
(1) 「時間だけではない」労災認定の視点を理解する
労災認定では、労働時間だけでなく、他の負荷要因も総合的に評価されます。自社に当てはまるものがないか、厳しくチェックする必要があります。
- 勤務時間の不規則性: 拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い、深夜勤務など
- 事業場外での勤務: 出張の多い業務など
- 心理的負荷を伴う業務: クレーム対応、ノルマが厳しい業務など
- 身体的負荷を伴う業務: 重量物を取り扱う業務など
- 作業環境: 高温・低温環境、騒音など
(2)長時間労働を是正する
過労死を防ぐための最重要課題は、長時間労働の撲滅です。
- 時間外労働の上限遵守の徹底: 法律で定められた上限(原則月45時間・年360時間など)を全社で正確に把握し、遵守する体制を構築します。
- 年次有給休暇の取得促進: 年5日の取得義務はもちろん、従業員が気兼ねなく休暇を取れる風土づくりを進めます。
- 勤務間インターバル制度の導入: 終業から次の始業まで一定の休息時間を確保する制度は、従業員の健康を守る上で非常に有効です。(働き方改革推進支援助成金も活用できます)
- 健康診断の実施と事後措置の徹底: 定期健康診断の結果に基づき、有所見者には産業医の意見を聞き、就業上の適切な措置を講じることは企業の義務です。
(3)ハラスメント対策を徹底する
現在、企業にはハラスメント防止措置を講じることが法律で義務付けられています。
- ハラスメント防止に関する共通認識の醸成:ハラスメントは決して許されない行為であることを、全従業員が認識することが重要です。
- トップメッセージの発信と周知: 経営トップがハラスメント防止の姿勢を明確に示し、全従業員に周知徹底します。
- 就業規則への明記: ハラスメントに関するルールを就業規則に明記し、禁止事項や処分などを明確にします。
- 実態把握と対策:アンケートの実施や意見箱の設置などを通じて社内の実態を把握し、必要な対策を講じます。
- 研修の実施: 全従業員を対象に、ハラスメント防止に関する研修を実施します。
- 相談窓口の設置:社内外に相談窓口を設置し、被害者が安心して相談
(4)メンタルヘルス対策を推進する
従業員の「心の健康」を守ることは、企業の責務です。
- 相談しやすい体制づくり: 産業医や保健師、外部相談窓口(EAP)など、従業員が安心して相談できる窓口を複数用意します。
- ストレスチェックの実施と活用: ストレスチェック(常時50人以上の事業場では義務)を実施し、個人のセルフケアを促すとともに、集団分析結果を職場環境の改善に繋げます。
まとめ
過労死は、従業員とその家族から未来を奪う悲劇であると同時に、企業にとっては信頼、人材、生産性のすべてを失いかねない経営上の最大のリスクです。
- 労働時間管理の適正化
- ハラスメントのない職場づくり
- そして従業員の心の健康への配慮
これらを一つひとつ着実に実行していくことが、過労死ゼロへの第一歩となります。
従業員一人ひとりの顔を見ながら細やかな対応するなど、従業員を大切にする経営を実践し、誰もが安心して働き続けられる企業を目指し、過労死のない社会を実現していきましょう。
今回のコラムは、以下の顧問の方にご監修いただきました。
西岡 敏成
ジェイエスティー顧問
・元兵庫県警警視長
・警備・公安・刑事に従事
・2002年日韓W杯警備を指揮後、姫路警察署長・播磨方面本部長を歴任
・元関西国際大学人間科学部教授
ジェイエスティーには危機管理エキスパートが複数在籍しております。
企業のセキュリティ対策やコンプライアンス強化はもちろん、個人情報保護や暴対法対策など、危機管理全般のご相談はジェイエスティーまで。
